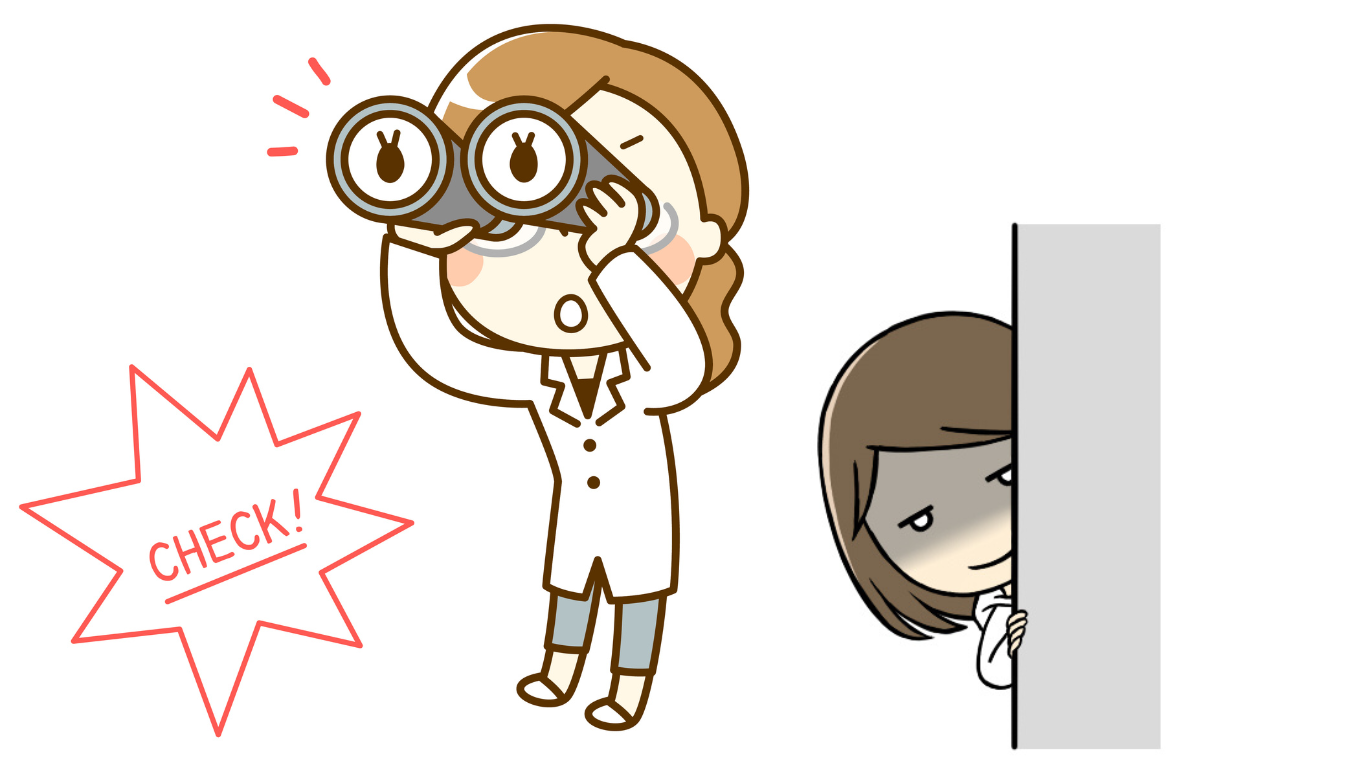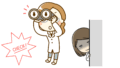⏳ 今日のテーマ:なぜあの人の話はいつもズレるのか?共感できないのに悪気はない、その脳の仕組み。
「台湾映画が好き」と言ったら「ジャッキーチェンですか?」
――思わず心の中でツッコむ、そんな“話のズレ”。
実はこの“会話のすれ違い”、性格の問題ではなく脳の情報処理のクセなんです。
共感が苦手なのではなく、「思考のルート」が違うだけ。
💬 会話がズレる人の脳の中では何が起きている?
①「連想回路」が先に動く脳
ズレ会話の人は、相手の話を聞いた瞬間に“意味”ではなく“連想”で反応します。
「韓国映画」→「アジア」→「ジャッキーチェン」と、脳内で一気に飛ぶ。
これはデフォルトモード・ネットワーク(DMN)が強く働いている典型です。
創造的で柔軟な脳の持ち主ですが、同時に「話題の文脈」をスルーしやすい傾向があります。
② 相手の意図より「自分の関連記憶」を検索
このタイプは、“相手が言った言葉”をトリガーに、過去の経験や知識を検索する脳の癖を持っています。
つまり、「言葉を聞いた瞬間に“自分の話”を思い出してしまう」。
だから悪気なく話を奪ってしまうのです。
🧠 共感ではなく“構造化思考”でつながろうとするタイプ
① 「人」より「情報」に注目
ジミーちゃんのような人は、感情よりも構造で理解する傾向があります。
「昭和歌謡=石原裕次郎」という反応は、“感情的共感”ではなく、“情報の分類”で会話している証拠。
② システマティック思考の強い人の会話特徴
- 感情よりも「理屈」で返す
- 共感よりも「補足・解釈」で返す
- 会話が「キャッチボール」ではなく「プレゼン」になりやすい
心理学ではこれをSystemizing傾向と呼び、知的職業・理系分野の人に多いタイプとされています。
🧩 「ズレている」=「想像力の方向が違う」だけ
① 感情ではなく“関連性”を想像する脳
このタイプは、相手の感情よりも「どんな関連があるか」を想像します。
つまり、「あなたの気持ちは?」ではなく「この話、何に似てる?」で考える。
そのため、共感の仕方が周囲とズレるのです。
② 「共感できない人」ではなく「別ルートで共感している人」
彼らは感情を理解できないわけではありません。
ただ、感情を言語化する前に理論化してしまう。
話を遮るように見えても、それは“理解を急いでいる”だけの場合が多いのです。
🧠 ズレ会話に疲れないための対処法
① 「ツッコミ」より「観察」に切り替える
「この人の脳、今どこを旅してる?」と観察視点に変えるだけでストレスは半減。
ツッコむより、“ルート探索”を楽しむと、会話が実験的に感じられます。
② 「なぜそう思ったの?」をやんわり聞く
連想型の人は、“理由を聞かれる”と整理が始まります。
「どうしてそう思ったの?」と促すだけで、ズレた会話が一気に落ち着くことも少なくありません。
🪞 まとめ|“ズレ”を笑える人は、人生がラクになる
- 会話のズレは「脳の回路の違い」
- 感情型と連想型では、世界の見え方が違う
- ズレを笑える人ほど、人間関係がラクになる
“ズレ”は欠点ではなく、思考の個性。
それを観測できるあなたも、もう心理観察者の仲間です。
🔗 関連記事
🔭 【観測日記#2】ジミー大西系整体師が放った謎の質問
🧠 【解説記事#4】雑談がズレる人の脳のクセ|なぜ会話が噛み合わないのか?