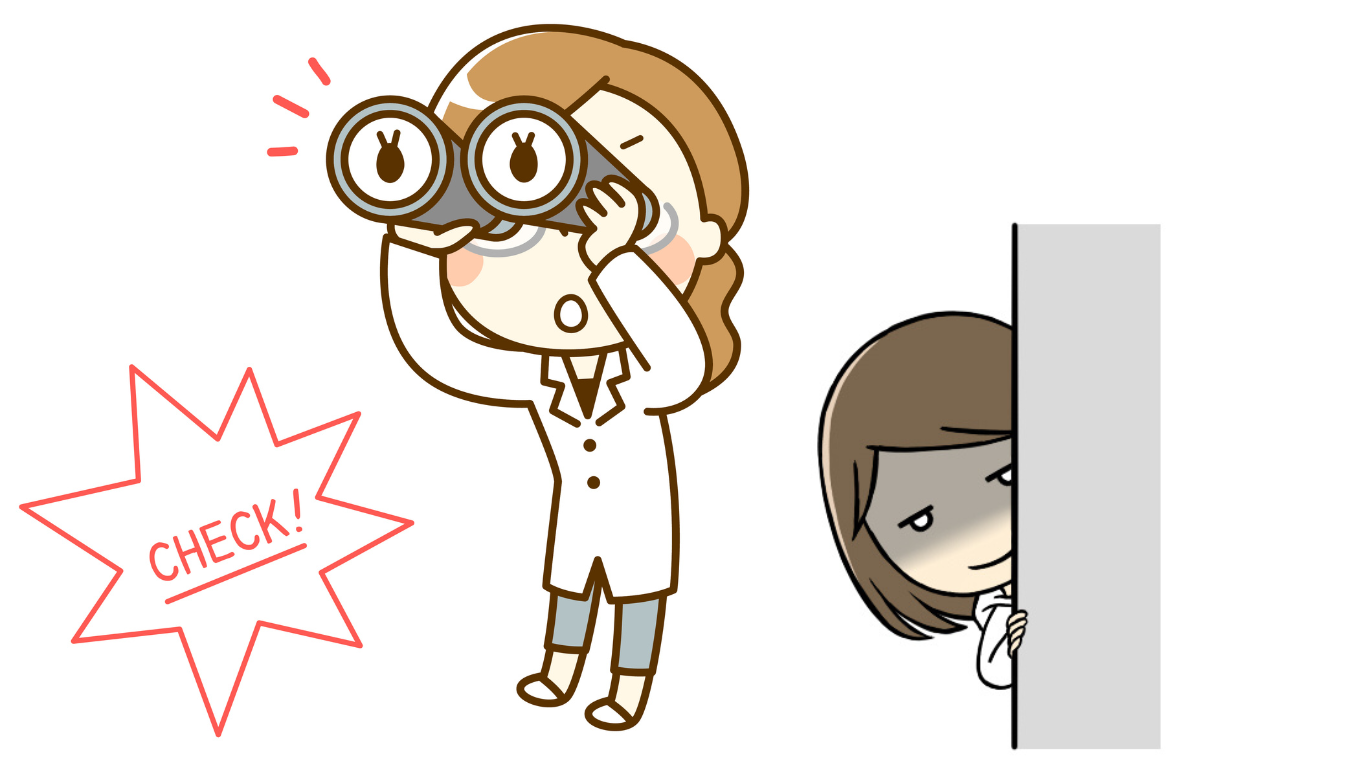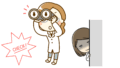⏳ 今日のテーマ:なぜ人は“逃げることで自分を守る”のか?
「できないのに“できます”と言う」
「苦手な領域を避けるために肩書を変える」
――そんな“逃避と保身”の行動を見たこと、ありますよね。
人は、能力の不足を隠すためではなく、存在の不安を鎮めるために逃げる。
今回は「理系詐称講師I」を題材に、自己防衛と回避の心理構造を解説します。
💬 自己保身の根っこは「存在不安」
① “できない”を認めることは、存在の危機
自己保身的な人は、失敗を「人格の否定」と感じやすい。
だから「苦手」や「不得意」を直視できない。
代わりに“肩書”や“理屈”で自分を守る。
心理学ではこれを 自己防衛機制(defense mechanism) のひとつ、「合理化」と「逃避」として説明します。

Iの“理系です~”は、自己紹介じゃなくて“自己防衛宣言”だったんです。

つまり“できない私”を消すための肩書操作ね。
② 嘘をついているわけではなく、“信じたい防衛”
逃避行動の多くは、意図的な嘘ではありません。
脳が現実をねじ曲げてでも「安心できる自分像」を維持しようとするからです。
心理的には「認知的不協和の回避」。
自分の理想と現実がズレたとき、理想側に合わせて記憶を再構成してしまう。

Iにとって“理系”は肩書じゃなく、不安を鎮める呪文だったんですね。

安心のためなら現実ごと変えるのが人間。
🧩 逃避が連鎖する職場心理
① “逃げ得構造”がチームを壊す
自己保身型の人は、自分のストレスを軽減するために他人の負荷を増やす。
結果、責任が連鎖的に転移し、チームが疲弊する。

Iが逃げた分、Aが夜中まで授業を背負う。

そしてEが“生活が…”って泣く。もう逃避の連鎖装置だね。
② 責任回避は“恥の恐怖”から生まれる
自己保身には「恥の回避」が強く関与します。
文化心理学的に、日本では「恥=社会的死」と感じる傾向が強いため、人は恥を避けるために“逃げ”を選びやすい。
能力不足より「恥をかくこと」の方が恐ろしい。
だから、嘘でも肩書を作り、自分を守る。

“できません”と言える人は、恥を受け入れられる人なんですね。

つまり“正直さ”って、勇気よりも“耐性”の話か。
🧠 自己保身タイプ3分類
| タイプ | 行動パターン | 心理の核 | 防衛の目的 |
|---|---|---|---|
| 回避型 | 苦手を避け、責任を他人に転嫁 | 不安回避 | 自己崩壊の予防 |
| 肩書操作型 | 肩書・立場で自分を守る | 承認欲 | 自己価値の維持 |
| 合理化型 | 言い訳・理屈で現実を調整 | 認知的不協和 | 心の整合性確保 |

Iは“肩書操作型”の典型。肩書が自己防衛の装甲なんです。

つまり、あれは“名刺で鎧を作る人”。
🧭 自己保身に巻き込まれないための観測スキル
① “肩書と中身”を切り離して観る
人の肩書をそのまま信じず、「どんな行動を取っているか」で観測する。
防衛的な人ほど、言葉と行動がズレるため、「何を言ってるか」より「何を避けてるか」を見るのがポイント。
② “防衛反応”を非難せず観測する
自己保身は、ほとんどが無意識。
だから「ずるい人」ではなく「不安な人」として観ることで、自分が巻き込まれるストレスが減ります。

“逃げてるな”と思ったら、追わずに観測。

逃げの奥にあるのは、恥と恐怖の防衛本能なんだね。
🪞 まとめ|逃げる人ほど“守りたい何か”がある
- 逃避は不安の防衛
- 肩書を変えるのは、自己否定の痛みを避けるため
- 自己保身は悪意ではなく、未処理の恐怖の表れ
人は“できる自分”より“安心できる自分”を選ぶ。
だからこそ、観測者は「逃げ」を非難せず、静かに見届ける。